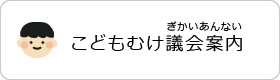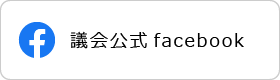にいがた市議会だより
第108号(令和7年2月2日) 3ページ
一般質問の要旨
- 一般質問者は22人です。質問項目は主なものを掲載しています。
- [答]の末尾にかっこ書きの記載がない答弁は、全て市長答弁です。
- 議会の録画中継画面は下の二次元コードからご覧ください。
12月定例会の録画中継は、次回の定例会の録画中継が開始されるまでの間ご覧いただけます。

新潟市公明党 志賀 泰雄

認知症理解に向けた体験型ワークショップとおくやみコーナー設置
[問]市民に認知症を自分のこととして感じてもらうには、座学だけでなく体験することが有効だと考える。子どもや若者、現役世代などが、気軽に参加できる体験型ワークショップで認知症の困りごとを体験し、理解者を拡大する取り組みが有効と考えるがどうか。
[答]認知症に関する体験型の学びは、共生社会の実現に重要な機会と考えている。小・中学生向け講座はすでに工夫しながら取り組んでいるが、大人向けの体験ができる講座も検討する。
[問]おくやみコーナーの設置は国を挙げて推進しており、ガイドラインも示されている。政令市でも14都市が設置済みであるが、本市の検討状況について伺う。
[答]他の自治体の設置状況や運用面の課題などは把握している。国の指針なども参考にしながら本市の方向性について検討を進める。
翔政会 内宮 貞志

発注工事の事業量確保・平準化と旧小須戸小学校跡地の利活用
[問]市内建設業者の安定的・継続的な事業量を確保するため、道路の維持修繕は債務負担行為や補正予算などにより工事発注の平準化が必要と考えるが、現状と今後の取り組みについて伺う。
[答]有利な起債などを活用した事業量の確保に努めるとともに、繰越明許費や債務負担行為の活用による工事発注の平準化を行うなど、引き続き可能な限り要望に対応していく。
[問]旧小須戸小学校跡地について、地元からは宅地化してほしいとの要望がある。人口減少が進む一方で、世帯数が増加している同地区において、若い世代が地元を離れないよう、住宅地の確保が必要と考えるがいかがか。
[答]現在、地域の要望を踏まえ売却に向けて検討している。今後は地元コミュニティ協議会と協議し、売却に向けた取り組みを進めていく。
翔政会 伊藤 健太郎

フリースクールの現状と世界遺産登録を活かすために
[問]不登校によって著しく学力が低下することは、学業の遅れや進路選択上の不利益、社会的自立へのリスクは大きい。市内には不登校の子どもの学習機会確保の受け皿となるフリースクールがあるが、現状を伺う。
[答]フリースクールでは、学習や相談カウンセリングなどを実施しており、本市ではフリースクール等連携協議会を主催し、教育関係機関の連携と協力のための協議を行っている。(教育長)
[問]佐渡島(さど)の金山の世界遺産登録は、本市にとって絶好のチャンスであり、緊迫感を持ってダイナミックに取り組んでいくべきだと考える。このチャンスを生かすための、本市の今後の取り組みについて伺う。
[答]今まで以上に情報発信の強化や受け入れ態勢の向上を図るとともに、さらなる誘客に向けて、官民一体となって全力で取り組んでいく。
ともに躍動する新潟 宇野 耕哉

子どもの生活・学習支援拡充と夜間中学のニーズ調査
[問]令和5年11月、こども家庭庁は、子どもの生活・学習支援事業の予算拡充を発表した。本市は「こどもまんなか応援サポーター」として活動すると宣言しているが、この事業の拡充に対応していない。この支援事業の拡充による受験料や模試費用補助の取り組みについて伺う。
[答]受験料などの補助については、他都市の実施状況を注視・研究しながら検討を進める。
[問]文部科学省は、夜間中学が各都道府県・政令指定都市に少なくとも1校、設置されるよう促進している。本市が令和6年9月に実施した夜間中学のニーズ調査の結果を伺う。
[答]夜間中学に入学する可能性のある方や支援者からの回答では、夜間中学に一定数のニーズがあると推察される。40から50代では「通ってみたい」という意見が多く、若年層には「夜間中学を知らせたい」という意見も多かった。(教育長)
無所属の会 中山 均

面的液状化対策の進捗(しんちょく)状況と地下水位低下工法の可能性と検証
[問]地震の被災地域では個別の修繕や対策を行っている住民もおり、地域全体の機運としては少し濃淡もあるように見える。その意味でも今後の明確な見通しや、随時の報告なども明らかにする必要があるが見解を伺う。
[答]関係する自治会と調整し、地域で説明会を開催するなど、引き続き詳細で丁寧な情報発信に努める。またデータ不足を補うため追加のボーリング調査を行い令和7年5月に完了する。
[問]液状化対策として下水道管に地下水を流す方法について9月定例会で否定的な答弁だったが、独立した排水管・排水装置の設置も相当のハードルがある。地盤や地下水量の評価を行い工法選択について今後検討を進めるべきでは。
[答]対象地に排水先が確保されているか、地下水位低下施設の施工が可能かなど、技術的な検証を実施した上で、工法の選択を行う。
市民ネットにいがた 石附 幸子

ささえあいセンターの役割と女性支援新法施行を受けて
[問]被災世帯へ個別訪問し、困りごとを聴き取り、内容に応じて専門機関につなぎ今後の支援方針を立てるスタッフは、ささえあいセンターの業務の要である。スタッフがこれまで以上に役割を果たすため、どう取り組んでいくか。
[答]被災者に寄り添った伴走支援に加え、ささえあいセンターの機能の充実を図るため、各セクションのスタッフのさらなるスキルアップに努め、今後はスタッフの増員も予定している。
[問]「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が2024年に施行され、民間団体と協働し多様な支援を包括的に提供することになった。本市の女性相談支援の中軸となる機能と女性相談支援員の資質向上について伺う。
[答]男女共同参画課が庁内を総括し、民間とさらなる連携で相談体制を強化し、支援員による切れ目ない相談支援と相談技術向上を目指す。
新市民クラブ 高橋 三義

庁内の行財政改革と補助金の在り方
[問]12年間の行財政改革によって196億円を削減したが、市民サービスや市民福祉の後退と見受けられるものもあった。今後は、負の遺産とならない持続可能な安定した財政運営をするために、庁内の行財政改革をどう考えるのか。
[答]持続可能な行財政運営を確立するため、経営資源の効果的な配分や簡素で効率的な組織体制の構築、自治体DXの推進などにより、本市が目指す都市像を実現していく。
[問]本年度の補助金総額は、401件で299億3千万円となっているが、経済の発展による市民所得や地価の上昇、市税収入の伸びにつながっていない。補助金の交付により、どのような効果があったと捉えているか。
[答]補助金の交付は、本市の政策や施策を実現するための具体的な取り組みの一つであり、市政運営の推進に寄与していると認識している。
翔政会 保苅 浩

農業振興地域整備計画における農用地区域の設定方針
[問]農用地区域の設定方針において、「集落内に介在する農地」は農用地区域に含めないと明記されているが、本市にはそのような農用地が実際には現存している。方針に沿わない農用地が存在するのであれば、方針に基づき修正すべきだと考えるが、それらの農用地の把握と今後の対応について伺う。
[答]農業振興地域の整備に関する法律で、土地改良事業の受益地については、集落区域内に介在する農地であっても農用地区域としている。基礎調査結果などを基に、引き続き適正な農用地の設定と運用に努めていく。
農用地区域
農業振興地域整備計画で定める区域のことで、集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行に係る区域内の土地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定され、農業以外の目的で土地を利用する行為が制限される。
日本共産党新潟市議会議員団 倉茂 政樹

県のPark-PFI計画中止と公契約条例制定による賃上げを
[問]Park-PFI制度は、民間に公園整備を行わせ、商業的活用を認めるものである。施設の建ぺい率を広げ、設置管理期間の20年の特例延長は、公共空間としての公園の役割と相いれない。県に計画中止を求めるべきでは。
[答]県のPark-PFI計画は、現在、民間事業者や団体から意見を募るサウンディング調査の段階であり、県の動向を注視していく。
[問]東京都墨田区は、2023年に賃金条項などを含む公契約条例を制定した。足立区や杉並区が実施したアンケートから、労働報酬下限額を設定した公契約条例が賃金を上げる効果は明らかである。本市も公契約条例を制定すべきでは。
[答]公契約条例は、公共事業のみ適用のため、地域内賃金の底上げ効果は限定的で、導入には課題が多い。持続的、構造的な賃上げのためにも事業者が賃上げしやすい環境を整えていく。