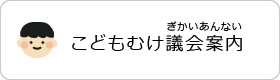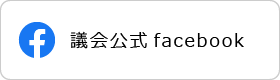にいがた市議会だより
第108号(令和7年2月2日) 4ページ
一般質問の要旨
- 一般質問者は22人です。質問項目は主なものを掲載しています。
- [答]の末尾にかっこ書きの記載がない答弁は、全て市長答弁です。
- 議会の録画中継画面は下の二次元コードからご覧ください。
12月定例会の録画中継は、次回の定例会の録画中継が開始されるまでの間ご覧いただけます。

翔政会 米野 泰加

栄養教諭の配置状況と通学に配慮を要する児童・生徒への対応
[問]国は栄養教諭の最低限の配置基準を定めているが、食物アレルギーの子どもが増え続ける今、働く環境として過酷である。国の配置基準と本市の配置状況を伺う。
[答]自校調理の国の定数は児童・生徒550人未満で4校に1人のところ、本市は2校に1人、給食センターは国と同程度で、1,500人以下で1人、1,501から6,000人で2人配置している。(教育長)
[問]児童・生徒が発達障がい通級指導教室に通う際は、保護者の送迎が必要であり、家庭の負担は大きい。送迎に時間がかかると通級指導を受けることをちゅうちょし、支援につながらないこともある。巡回指導や距離的配慮をした通級指導教室を増やせないか。
[答]在籍校から通級校まで遠距離の児童・生徒については、拠点校、巡回校の新増設を計画的に進めることで解消を図っていく。(教育長)
翔政会 西脇 厚

震災による液状化対策への取り組み
[問]震災被害の対応はさまざまあるが、被害に遭われた住民の生活や健康が一番大事である。今後、住宅の傾きに大きな影響を与えている液状化現象の追加調査が始まる。ボーリング調査が27カ所追加されたが、地域によってボーリング調査に偏りがある。このボーリング調査の詳細と具体的な取り組みを伺う。
[答]調査は関係自治会と調整し、併せて地域説明会を開催するなど丁寧な情報発信を行う。江南区天野地区では、6カ所の既存データの活用ができたため3カ所で追加のボーリング調査と地下水位観測を実施し完了は5月中旬の予定。

液状化対策のためのボーリング調査
新風にいがた 小林 裕史

防災ハンドブックの作成と中小企業の価格転嫁支援
[問]防災情報の周知のため、デジタル媒体が活用されているが、停電時はデジタル情報を見ることができず、高齢者はデジタル機器の操作が不慣れなどのデメリットがある。紙媒体の防災ハンドブックが有効と考えるがいかがか。
[答]紙媒体は情報の入手や内容の把握が容易である一方、即時での情報更新が困難などの短所がある。デジタルと紙の長所・短所や、情報の種類・対象者に応じた発信となるよう努める。
[問]消費を強くし経済の好循環を生むためには賃金を増やす必要があるが、中小企業は賃金などのコスト上昇分を価格に転嫁できず苦しんでいる。国や県の支援に加えて本市も支援策を強力に講じる必要があると考えるがいかがか。
[答]設備の導入などによる業務効率化や生産性向上を図ることが価格転嫁対策になると考えるが、今後、支援策についても検討していく。
ともに躍動する新潟 細野 弘康

新潟市こども計画の特色と自治会・町内会のICT化
[問]「新潟市こども計画」は、これまでの子ども施策を統一的にまとめ、全体像を市民にとって分かりやすくするもので、令和7年4月から開始する。今まで以上に全庁を挙げて子ども・若者支援を進めるための計画にすべきと考えるが、本市の計画の特色を伺う。
[答]令和4年度に新潟市子ども条例を施行し、子どもの権利保障や子どもの意見聴取の取り組みに着手したことで、本計画案にも子どもの意見を反映させた施策を盛り込むことができた。
[問]自治会の役員や住民の負担軽減のためには、ICTの導入が不可欠である。現在、自治会向けにさまざまなスマートフォン向けアプリが提供されているが、本市の今後の取り組みを伺う。
[答]独自にICT化に取り組んでいる自治会と意見交換を行い、さまざまな自治会・町内会にとって最も効果的な支援策を検討していく。
翔政会 土田 真清

イノシシなどの野生大型獣対策と西蒲区のまちづくり計画
[問]近年、イノシシなどの野生大型獣が人の生活圏域に出没し、農業にも大きな影響を及ぼしており、農業従事者やJAなどと連携した対策が必要である。国の支援制度を活用し、増え続ける野生大型獣対策に取り組むべきでは。
[答]イノシシをはじめ、本市全体の鳥獣被害の状況を把握するとともに、地域の意向を伺いながら、国の支援制度の活用を検討していく。
[問]西蒲区役所建て替えや巻駅周辺整備事業などは、区別構想の実現に向けた重要な施策である。これらの事業を契機に、巻地区中心市街地の再生に向け、道路整備など新たなまちづくり計画が必要と考えるがどうか。
[答]現在取り組んでいる「区ビジョンまちづくり計画」を着実に実行しながら、当地区の将来にとって重要な基盤となるものをどのように形にしていくか、検討を進める。
若者の議会への関心を高めるための取り組み
主権者教育の推進
新津第二中学校(秋葉区)
主権者教育は未来の有権者が選挙や地方自治制度への理解を深め、自分たちの住む地域社会の諸課題を見いだし、課題解決に向け自ら参画しようとする意欲を醸成する取り組みです。
市議会では、主に中学・高校を対象に、学校が実施する主権者教育に協力しています。
11月13日に議員10人が同校を訪れ、3年生約200人にロールプレイング方式の模擬市議会と意見交換を行いました。生徒からは、「市議会について改めて興味を持つことができた」「市議会議員の考えを知ることができて貴重な経験になった」「18歳になったらしっかり選挙に関わりたい」などの感想がありました。
市議会は、今後も主権者教育の推進に協力していきます。


動く市政教室「チャレンジ『子ども議会』」を開催
模擬市議会を通して市議会に関心をもってもらおうと、動く市政教室の企画で11月16日に「チャレンジ『子ども議会』」が開かれました。
この日は小学3から6年生と保護者5組10人が参加し、議会事務局の職員から市議会について説明を受けた後、議場で「子ども議会」に臨みました。子どもたちはそれぞれ議長役、議員役、市長役を務め、賛成・反対討論、採決までの流れを学びました。
この後、議長室や全員協議会室、傍聴席などを見学し、「実際の議会の進み方が分かった」「市長役は議案が提案できて楽しかった」「いろいろな部屋を回って貴重な体験ができた」などの感想がありました。