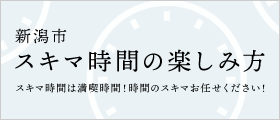市報にいがた 令和7年2月16日 2833号 1面・2面
私たちも幸せに暮らしたい 届け。犬・猫の願い

- 目標 11:住み続けられるまちづくりを
- 目標 15:陸の豊かさも守ろう
- 目標 17:パートナーシップで目標を達成しよう
問い合わせ 動物愛護センター(中央区清五郎 電話:025-288-0017)

犬や猫を飼いたいと思っている人へ
ペットを飼うことは命を預かることです。責任を持って世話をできるか、よく考えてみましょう。
飼う前に考えてほしいこと
- 住居がペットを飼える環境か
- 飼いたいペットについて正しい知識があるか
- 家族全員がペットを飼うことに賛成しているか
- 家族にアレルギーはないか
- 毎日欠かさずペットの世話に時間と手間をかけられるか
- ペットの世話をできる体力があるか
- 近隣に迷惑をかけないように配慮できるか
- ペットを飼い続けるための費用があるか
- 高齢になったペットとの生活を想定できているか
- 万が一、ペットを飼えなくなったときの預け先があるか
みんなが関心を持つことで救える命がある
犬や猫の殺処分数は減少傾向にありますが、ゼロになったわけではありません。飼育に責任を持つことや、譲渡という手段を検討することで救える命が身近にあることを、多くの人に知ってもらい、動物愛護に関心を持ってもらえるとうれしいです。

新潟市動物愛護協会 理事
伊勢 みずほさん
犬や猫を飼っている人へ
犬や猫も社会の一員です。マナーを守って安全に飼いましょう。
今どきの犬の飼い方
室内で飼う
犬は群れで暮らす習性があるため、屋外の犬小屋にいるよりも、飼い主のそばで暮らすほうが幸せです。また、冬の屋外飼育は老犬にとって厳しい環境です。
メリット
- 犬にとって快適な生活環境になる
- 犬の変化に気付きやすく、健康管理しやすい
不妊去勢手術をする
犬は生後6カ月程度で手術を行うと特に効果が高く、性格が穏やかでしつけやすくなります。
メリット
- マーキング(電柱などに尿をかける行動)が減る
- 前立腺や子宮の病気にならない
ふんや尿は自宅で済ませる
散歩に行く前に、自宅敷地内を歩かせて排せつをしたら褒め、その後散歩に行くようにすると、上手にしつけることができます。
メリット
- 近所迷惑にならない
- ふんや尿の始末がないので安全に散歩できる
※関連記事「犬の飼い方相談会」を別冊情報ひろば2面に掲載
今どきの猫の飼い方
室内で飼う
猫は狭い縄張りでもストレスなく生きられる動物です。猫が好きな爪研ぎを用意すれば、家具が傷つけられることも少ないです。
メリット
- 近所迷惑にならない
- 病気にかかりにくい
- 交通事故に遭わない
不妊去勢手術をする
猫は生後4カ月から5カ月程度で妊娠可能となり、発情期に外に出してしまうと、ほぼ100パーセント妊娠します。妊娠させるつもりがなければ、手術をしたほうが猫も飼い主もストレスなく暮らせます。
メリット
- 望まない繁殖を防ぐことができる
- 発情期特有の大きな鳴き声がなくなる
首輪と迷子札を着ける
「もしものとき」のため、飼い主の名前と連絡先が分かるようにしておきましょう。
保護犬・猫を家族の一員として迎え入れてくれる人を募集しています

譲渡の流れ
1 譲渡対象の犬・猫を確認
動物ふれあいセンターや動物愛護センターのホームページで、対象の犬・猫を確認する。 ※対象の犬・猫は、両センターで実際に会うことが可能
2 譲渡資格調査票などを提出
迎え入れたい犬・猫がいたら、調査票などを動物愛護センターへ提出する。 ※調査票などは新潟市ホームページに掲載。動物ふれあいセンターや動物愛護センターでも配布。書類審査が終わり次第、譲渡前講習の日程などをお知らせ
3 譲渡前講習・面談・お見合い
正しい飼い方やマナーなどについての講習を受ける。また、譲渡を希望する犬・猫とお見合いをして、実際に飼うときの注意点などを確認する。
トライアル飼育ができます
犬や1歳以上の猫の場合、希望する人は講習後に最長2週間、お試しで飼育できます。
譲渡後の生活を想像したり、先住ペットとの相性を確認したりすることができます。

4 譲渡
譲渡が決定したら、脱走しないようにケージやキャリーバッグなど適切な方法で、自宅へ迎え入れる。
※譲渡後は動物病院で健康診断を受けてください
すてきな出会いを見つけに来ませんか 猫の譲渡会を開催

予約不要で参加できます。
日時 3月9日(日曜)午後1時から午後3時
会場 動物愛護センター
参加費 無料
※混雑状況により、入場を制限する場合あり。譲渡条件など詳しくは新潟市ホームページに掲載
保護猫を迎え入れた人に聞きました こどものように大切な存在

島倉 司さん
うにちゃん(左)・ほたてちゃん(右)
(中央区在住)
猫が大好きで、こどもの頃からずっと猫を飼いたいと思っていました。
昨年7月、妻の知人のミルクボランティアさん(下記)から「生まれたばかりの子猫を保護した」と教えてもらって会いに行ったのが、「うに」との出会いでした。娘と息子が動物の世話をできる年齢になっていたことや、家族みんなが賛成してくれたことで、うにを飼うことに決めました。うには生まれてすぐに親猫が逃げてしまったため、周囲と関わることが苦手な猫でした。「周りとの関わり方を知ってほしい」「寂しい思いをしてほしくない」という気持ちもあり、2カ月違いで家に迎え入れたのが「ほたて」です。ほたてもミルクボランティアさんからの紹介で譲り受けた保護猫でした。うにとほたては、けんかもしながら、きょうだいのように仲良く暮らしています。
うにとほたてを迎え入れてからは、こどもたちが二匹の世話はもちろん、世話以外の家事も率先して手伝ってくれるようになり驚きました。
猫がいる幸せな生活をこれからも続けられるように、責任を持って一緒に暮らしていきたいです。

きょうだいのように仲の良い「うにちゃん」と「ほたてちゃん」
子猫の世話をするミルクボランティアを募集
保護されている子猫を、生後2カ月になるまで自宅で世話するボランティアを募集しています。世話の内容は、ミルクや餌やりのほか、トイレ・ケージの清掃、健康観察、ふれあい遊びなどです。 ※応募条件・方法など詳しくは新潟市ホームページに掲載

ボランティアの主な条件
- 市内在住で、子猫の飼育が可能な住居に住んでいる
- 自家用車で子猫の送迎ができる
- 子猫を適正に飼育できる環境があり、家族全員が飼うことに同意している
- 事前に行う説明会や個人面談に参加し、家庭訪問を承諾できる

保護猫などの情報はこちらもチェック!
新潟動物ネットワーク
新潟動物ネットワーク(NDN)は、主に猫の保護・譲渡に取り組むボランティア団体です。NDNにも飼い主を募集している猫などが登録されています。ぜひ確認してください。
Instagram(インスタグラム)をチェック!
動物愛護センター公式アカウントで情報を発信中
保護犬・猫の写真や動画、イベント情報などを発信しています。ぜひフォローしてください。
野良猫のふんなどで困っている人へ
野良猫が住み着く原因
誰かが餌をあげているなど、猫にとって住みやすい環境になっている可能性が高いです。
野良猫が寄ってこないようにするには
猫の侵入経路や、排せつ場所などを調べてから対策すると効果的です。
対策例1 園芸用木酢液を家の敷地(猫の侵入口など)にまく
木酢液(もくさくえき)は、猫が苦手な木が焼けた酸臭を放ちます。
※使用する場合は、ふんなどの臭いを取り除いてから、繰り返し散布すると効果的
対策例2 超音波発生装置を設置する
動物愛護センターや区役所区民生活課で、超音波発生装置(ガーデンバリア)を2週間、無料で貸し出しています。
駆除目的の捕獲・引き取りはできない
動物愛護センターや区役所では、駆除目的での野良猫の捕獲・引き取りをしていません。ふんなどの被害を受けている場合は、自らで対策するしか方法がありません。
野良猫の寿命は3年から5年ほど
野良猫を迷惑に思っている人もいると思いますが、野良猫もまた被害者です。元飼い猫が、心無い飼い主に捨てられ、つらく厳しい野良生活を送っているのです。
野良猫は寒さや病気、交通事故のため、寿命が3年から5年程度と言われています。繁殖さえしなければ、長い間迷惑をかけるものではありません。不妊去勢手術された野良猫は、当代限りの命として、できるだけ見守ってあげてください。 ※野良猫の不妊去勢手術について、詳しくは動物愛護センターへ問い合わせ


 閉じる
閉じる