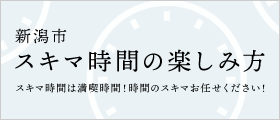地域包括ケアシステムについて
地域包括ケアシステムとは
高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供できるサービス体制です。本市では地域包括ケアシステムを深化・推進させるため、各分野でさまざまな取組みを進めています。
本市の地域包括ケアシステムを深化・推進させるための重点的取組事項
1 支え合いのしくみづくりの推進
地域包括ケアシステムにおいては、支え合う地域づくりが大切です。地域の茶の間などをはじめとした住民が主体の生活支援が一人一人の介護予防・健康づくり(健康寿命の延伸)につながることを目指します。
また、こうした支え合う地域づくりが、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていける地域共生社会の構築にもつながることから、地域の多様な主体が協働する取組を支援していきます。
2 介護人材確保の取組の強化
現役世代が減少する中においても、介護現場が地域における介護ニーズに応え、職員がやりがいを持って働き続けられる環境づくりを進めるために、介護という仕事の魅力発信、介護分野で働く人材の確保・定着などの取組について、関係機関と連携しながら進めていくことが重要です。
本市では、「介護の魅力発信」、「新たな介護人材や多様な介護人材の確保」、「介護人材の定着支援」の3つの視点から各種施策に取り組むとともに、国や県、介護サービス事業所、介護福祉士養成校、その他介護人材に関わる機関と連携して介護人材確保対策を推進します。
3 在宅医療・介護連携の推進
医療と介護のニーズを併せ持つ慢性疾患や認知症等の高齢者の増加が見込まれることから、入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等さまざまな局面において、地域における在宅医療や介護の提供に携わる関係者が連携し、切れ目なく一体的に支援できる体制構築に向けた取組を推進していきます。
また、在宅医療を担う医師や看護師などの人材確保や、人生の最終段階における医療、看取り等への市民の理解を深めるための普及啓発をさらに強化して取り組みます。
4 認知症施策の推進
急速な高齢化に伴い、認知症の人は年々増加していることから、認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社会の構築は、今後ますます重要となってきます。
国においては、認知症の人を含めた国民一人一人が個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合う共生社会の実現を推進することを目的として、認知症基本法を制定しました。今後は、同法の内容や今後示される国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、「正しい知識と理解の普及」、「予防・社会参加」、「医療・介護連携による切れ目のない支援」、「認知症に理解ある共生社会の実現」といった施策を推進し、共生社会の実現を図ります。
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた地域包括ケア計画の策定
高齢者の健康づくりや生きがいづくり、介護サービス基盤の整備など、本市の高齢者施策について総合的かつ計画的に進めていくため「地域包括ケア計画」を策定しています。
同計画は、その基本理念を「自分らしく安心して暮らせる健康長寿社会の実現」とし、「予防」、「生活支援」、「介護」、「医療」、「住まい」、「認知症」に関わる各種施策を展開しています。
新潟市地域包括ケア計画[新潟市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画]
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1281 FAX:025-222-5531

 閉じる
閉じる