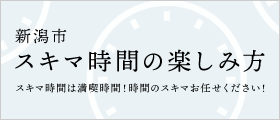生食用食肉取扱いの制度
令和4年9月、京都府でレアステーキと称するユッケ様の食品等を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157食中毒が発生しました。
生食用食肉については規格基準が定められており、これに該当しない食肉については、食中毒防止の観点から、中心部を75℃で1分間以上又はこれと同等以上の加熱効果を有する方法により加熱調理を行う必要があります。
今一度、下記についてご確認ください。
- 生食用食肉を取り扱う場合には、下記「生食用食肉の規格基準」に適合する必要があります。
- 生食用食肉を加工又は調理する場合には「新潟市認定生食用食肉取扱者養成講習会及び取扱施設の届出に関する要綱」に基づく届出が必要です。
なお、生食用食肉であっても、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方にあっては、発症すると重症化しやすいため、喫食しないよう細心の注意を払ってください。
生食用食肉の規格基準について
平成23年4月に発生した飲食店チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒を受けて、厚生労働省で罰則を伴う強制力のある規制として、生食用食肉に関する規格基準を制定し、平成23年10月1日から施行しました。
- 生食用食肉として販売する際には、生食用食肉の加工基準、成分規格及び保存基準に適合したものであることを確認してください。
- 生食用食肉を取り扱う飲食店営業の施設において、生食用食肉を調理する際は、速やかに提供して消費者に喫食させる必要があります。持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)をする場合は、中心部まで十分に加熱調理したものを提供してください。
- 加熱調理が完全に行われていない食肉等を提供し、消費者が最終加熱を行い喫食する場合は、安全に飲食できる加熱の具体的な方法を、口頭による説明のみではなく、掲示等により確実に情報提供を行ってください。
- 食肉の表面を焼いた後に冷却したもので、中心部まで十分に加熱されていないものは、生食用食肉として取り扱ってください。
生食用食肉の規格基準
生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であって、生食用 として販売するものに限る。)の規格基準 (外部サイト)
![]()
生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&A(厚生労働省PDF)(外部サイト)
![]()
新潟市認定生食用食肉取扱者養成講習会及び取扱施設の届出に関する要綱について
新潟市では、規格基準で規定された内容が確実に守られるように、生食用食肉の加工や調理(※)を行うための届出や講習会について、別紙要綱の通り定めています。
- 生食用食肉を加工または調理しようとする施設は、施設基準に合致した施設(個別基準)を用意した上で、要綱に基づく「生食用食肉取扱施設及び認定生食用食肉取扱者届」の届出が必要です。
- また、生食用食肉を加工する施設の「認定生食用食肉取扱者」となる人は「認定生食用食肉取扱者養成講習会」の受講が必要です。
※加工とは:肉塊を枝肉から切り出したり、切り出した肉塊の加熱殺菌等を行うことをいう
※調理とは:加熱殺菌済みの生食用食肉の肉塊を細切又は調味して消費者に提供する行為のみを行うこと(加熱殺菌済みの生食用食肉の盛り付けのみを行う行為も含む。)をいう
新潟市認定生食用食肉取扱者養成講習会及び取扱施設の届出に関する要綱
![]() 新潟市認定生食用食肉取扱者養成講習会及び取扱施設の届出に関する要綱(R6.9.1一部改正)(PDF:326KB)
新潟市認定生食用食肉取扱者養成講習会及び取扱施設の届出に関する要綱(R6.9.1一部改正)(PDF:326KB)
生食用食肉を加工または調理しようとする施設に必要な施設基準(個別基準)
![]() 生食用食肉の加工および調理をする場合の施設基準(個別基準)(PDF:132KB)
生食用食肉の加工および調理をする場合の施設基準(個別基準)(PDF:132KB)
この他に、施設の共通基準及び営業許可の業種ごとの基準に合致する必要があります。
詳しくは「営業許可・営業届け出の業種について」のページをご確認ください。
牛レバーを生食用として販売・提供することは、禁止されています(平成24年7月から)
- 平成24年7月から、食品衛生法に基づいて、牛のレバーを生食用として販売・提供することを禁止されています。
加熱用を除き、生のレバーは販売・提供できません。
- レバーは「加熱用」として販売・提供しなければなりません。(いわゆる「レバ刺し」の提供はできません)
- 牛のレバーを販売・提供する場合には、レバーの中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
- 牛のレバーを使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
![]()
豚のお肉や内臓を生食用として販売・提供することを禁止(平成27年6月から)
- 平成27年6月12日から食品衛生法に基づいて、豚のお肉や内臓を生食用として販売・提供することを禁止されています。
加熱用を除き、生の豚のお肉やレバーなどの内臓は販売・提供できません。
- 豚のお肉や内臓は「加熱用」として販売・提供しなければなりません。(いわゆる「レバ刺し」などの提供はできません。)
- 豚のお肉や内臓を販売・提供する場合には、十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
- 豚のお肉や内臓を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
![]()
関連リンク
お肉はよく焼いて食べよう(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
![]()
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()

 閉じる
閉じる