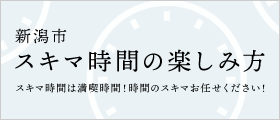(6-10)措置入院に対する説明不足
(6-10)措置入院に対する説明不足
令和6年7月25日苦情申立書受理
申立ての趣旨(要約)
令和4年に、私の次男が新潟県A保健所の措置によりB市のB病院に措置入院となった。その後、新潟市に転入したが、新潟市の担当部署は退院までの間に行政の役割や支援制度などについて、本人や家族に対し説明も無く役割を果たしていない。また、退院までに要した期間に納得できない。
所管部署
保健衛生部こころの健康センター(以下「所管課A」という。)
福祉部障がい福祉課(基幹相談支援センターB)(以下「所管課B」という。)
C区健康福祉課(以下「所管課C」という。)
調査の結果の要旨
令和6年12月27日決定
申立人の主張及び所管課の説明と双方から提出のあった資料に基づき、当審査会では以下のとおり判断し調査結果とします。
第1 事実経過
所管課Aの記録によれば、本件の事実経過は次のとおりです。
(1)令和4年2月20日、申立人次男が措置入院(B病院)。事案が新潟県A保健所管内で発生した関係で、新潟県A保健所が措置入院の手続を実施。
(2)令和4年3月24日、医師の判断をもとに、新潟県A保健所が措置解除の手続きをとり、申立人次男の措置入院が解除。その後は任意入院で入院継続(B病院)。
(3)令和4年6月10日、新潟県A保健所から所管課Aへ連絡。申立人の新潟市への転居に伴い、新潟市へ措置入院者退院後支援のケースとして引き継ぎたい旨の一報。
(4)令和4年6月18日、申立人が新潟市へ転居。
(5)令和4年7月12日、B病院で、申立人次男に関するカンファレンス実施。参加者は、申立人、申立人次男、B病院、新潟県精神保健福祉協会、所管課A及び所管課B。同カンファレンスでは、担当医師から、申立人次男の症状等から保護的な環境下で生活し、ストレスに対する対応能力を上げていくことが重要との意見があった。その上で、申立人次男については任意入院のまま新潟市内のD病院へ転院し、その入院中に、退院後の生活に向け、障害福祉サービスの利用を中心に検討していくとの方針となった。
(6)令和4年7月14日、申立人次男がD病院へ転院(任意入院継続)。D病院入院中は、病院の相談員が中心となり、所管課B、所管課C及び相談支援事業所等が連携し、申立人の次男や申立人の意向を確認しながら退院後の支援体制の調整が行われた。
(7)令和4年9月20日、関係者カンファレンス実施。参加者は、D病院、所管課A、所管課B、所管課C、相談支援事業所及び新潟県精神保健福祉協会。申立人と申立人次男の意向を参加者間で共有し、今後の進め方について検討した。
(8)令和4年10月4日、D病院相談員と所管課Aが電話の上、申立人次男の診断名や病状などから、本ケースの支援は、精神科医療中心ではなく、環境調整等を重視し、障がい福祉サービスを中心に考えていくという方針を再確認。その後、所管課Aは、1~2ヶ月毎に病院や所管課Bと電話連絡により進捗状況の確認を行っていた。
(9)令和5年4月24日、関係者カンファレンス実施(D病院)。参加者は、D病院、所管課A、所管課B、相談支援事業所。情報共有と退院に向けてのスケジュール確認を行う。
(10)令和5年5月24日、医療保護入院に切り替え入院継続(D病院)。決まりかけていたグループホームから入所を断られたことで、申立人次男の精神状態が不安定となり、任意入院から医療保護入院に切り替わる。
(11)令和5年6月12日、申立人次男の精神状態が安定したため、医療保護入院から任意入院に切り替え入院継続(D病院)。
(12)令和5年7月20日、D病院相談員と所管課Aが電話により情報共有。申立人次男の入所先グループホームが決まり、同年8月4日退院予定となる。
(13)令和5年7月24日、所管課AがD病院を訪問して申立人次男と面談。措置入院者の退院後支援の制度について改めて説明した上、入院中に地域の支援体制が整い、計画相談を担当する相談支援事業所が中心となり、障がい福祉サービスを組み立てていることから、所管課Aでは退院後支援計画は作成しないこととする旨申立人次男に伝える。
(14)令和5年8月4日、申立人次男がD病院を退院し、新潟市内のグループホームに入所。
第2 審査会の判断
1 申立人の苦情内容は、令和4年に申立人次男が新潟県A保健所の措置によりB病院に措置入院となり、その後、新潟市に転入したが、新潟市の担当部署は退院までの間に行政の役割や支援制度などについて、本人や家族に対し説明も無く役割を果たしていない。また、退院までに要した期間に納得できないというものです。具体的には、申立人の主となる相談先は所管課Aであるにもかかわらず何も役割を果たさず、退院が決まった時には「これで支援を終了する」と次男に言ったこと。また、所管課Bからは、申立人や申立人の次男の意向とかけ離れた支援策を提案されたことで、申立人次男が極度の行動に出ることを恐れていたが、所管課Bはそういった気持に寄り添ってくれず、信頼関係を築くことが難しかった。このように、制度を利用していく際の不安を、申立人も申立人の次男も相談したり、舵を取ってくれる人が新潟市にはおらず、申立人家族は路頭に迷ったとのことでした。
2 これに対する各所管課の回答内容の概要は次のとおりです。
(1)所管課A(保健衛生部こころの健康センター)
本件は約1か月で行政処分としての措置入院は解除となっている。その後の申立人次男の入院は、任意入院および医療保護入院で、これらの入院については、医師の判断と本人や家族の同意により病院との治療契約として行われるため、その決定に当センターを含む行政の関与する余地はない。
また、申立人の次男が新潟県A保健所の措置により措置入院となり、新潟市への転居に伴い当センターが措置入院者支援のケースとして引継いだことは事実であるが、令和4年7月のカンファレンス(申立人の次男、申立人も同席)で、退院後の支援体制については、精神科医療中心ではなく、障がい福祉サービスを中心に考えていくこととなったことから、障がい福祉を担当していない当センターは、病院や本市障がい福祉担当機関である所管課B及び所管課Cと連携をとりながら進捗状況の確認を行ってきた。その上で本ケースでは、措置入院の解除後も、入院を継続(任意入院と一時的に医療保護入院)し、所管課Bと相談支援事業所が中心となり退院後の支援体制の調整が行われていたが、申立人と申立人の次男の意向の違いや受け入れ先施設の辞退などで時間を要したものと認識している。入院の継続や退院後の入所先の調整の進捗状況については、病院や所管課B、相談支援事業所、所管課Cが随時申立人の次男、申立人に説明を行い、同意、了解を得た上で進めていたものと確認している。
(2)所管課B(福祉部障がい福祉課(基幹相談支援センターB))
令和4年7月26日に申立人の次男とD病院が面談をした際の情報を共有し、申立人次男の希望、申立人の希望に相違があることを確認した上で、どのような地域生活の方法が良いのかを確認した。令和4年8月30日には申立人及びその次男に障がい福祉サービスの説明をし、生活の方法について一緒に考えていくことを提示した。併せて、地域生活の準備を整えていけるだけの期間としてのおおよそのゴールを示し説明した。当課としては退院までに要する期間について関与する立場にない。
(3)所管課C(C区健康福祉課)
当課では、障がい福祉サービスの利用希望の相談があった場合、本人や関係者に対し、障がい福祉サービス利用までの流れや手続きにかかる事項について説明を実施する。また、障がい福祉サービス以外でも必要な支援や制度についてはその都度説明を行う。本件についても同様に、障がい福祉サービス利用に必要な内容について説明を実施し、障害福祉サービス申請の受付や障がい支援区分認定調査、利用先決定の連絡を受けての受給者証交付の手続き等を行った。
申立人次男の入院期間については、その決定に当課が関与するものではないため、退院までに時間を要したことについて説明はしていない。
3 以上を踏まえ当審査会は次のとおり判断します。
まず、本件で、申立人次男は、令和4年3月24日に措置入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条)が解除され、その後の入院は任意入院または医療保護入院であるところ、行政処分である措置入院とは異なり、任意入院は本人の同意に基づくものであり、また医療保護入院は精神保健指定医の診断の下、家族等の同意の下で行う入院であって(同第33条)、本件の各所管課は申立人次男の任意入院または医療保護入院の退院時期等について関与できる立場にはありません。そして、令和4年6月18日に申立人が新潟市へ転居し、同年7月14日に申立人次男がD病院へ転院(任意入院)した以降は、各所管課は、申立人次男の入院先であるD病院の相談員等と連携し、申立人ないし申立人次男の意向を適宜確認の上、退院後のグループホーム入所に向けた調整を行い、その中で適宜、申立人らに対して説明を行っていたことが認められます。
また、申立人次男が退院までに時間を要したのは、申立人と申立人次男の意向の違いや、申立人次男の精神状態の変化、受入れ先施設の辞退や調整等で時間を要したためであって、各所管課の業務遂行等に過誤等があったとは言えないと考えます。一般的に、措置入院解除後、任意入院等を継続している場合、新規の障がい福祉サービス利用の検討にあたっては、その決定までに時間を要することは少なくありません。入院中の場合、ご本人の病状、病院の外出許可と事業所や相談支援員との日程調整、サービス開始時期、退院時期の決定との兼ね合いがある等の点から事業所の確定が難しいことが要因と考えられます。本件でも申立人次男が希望しかつ空きのあるグループホームについて計画相談員等が調整していたところ、当初入所予定のグループホームから入所を断られたことや、申立人次男が精神的に不安定となり医療保護入院に切り替わること等もあり、グループホームの決定及び退院までに時間を要したと考えられます。
以上のことから、各所管課はそれぞれが所掌する業務を遂行するにあたり、特段の過誤等があったとは認められないと判断します。
一方で、申立人としては、「制度を利用していく際の不安を、申立人も申立人の次男も、相談したり舵を取ってくれる人が新潟市にはおらず、私たち家族は路頭に迷った。」と述べています。本ケースの支援においては、本市の体制上複数の所管課が関与している状況にありますが、このような気持ちを抱かせてしまった原因の一つとして、各所管課が担当している分野や業務について支援開始当初に説明していないことが考えられます。具体的には、所管課Aは精神保健福祉を担当する部署であり、障がい福祉は担当していないため、所管課B、所管課Cが主となり支援を進めて行くことの説明と理解を求める必要があったものと考えられ、今後はそのケースごとに説明の必要性を判断し対応されることを希望します。
また、業務の遂行に特段の過誤は認められないものの、要支援者が不安をいだくこととなったことは事実であり、そのような不安を抱かせないよう寄り添った対応が望まれることは言うまでもないことであり、今回のケースを今後の業務遂行に活かしていただきたいと思います。
以上、調査の結果、当審査会は、本申立てについて、新潟市行政苦情審査会規則第16条第1項に基づく、市長への意見表明ないし提言をする必要性はないものと判断致します。
規則第16条第1項
審査会は、苦情等の調査の結果、必要があると認める場合は、市長等に対し、当該苦情等に係る市の業務について、是正その他の改善措置(以下「是正等」という。)を講ずるよう意見を表明し、又は制度の改善を求める提言をすることができる。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

 閉じる
閉じる