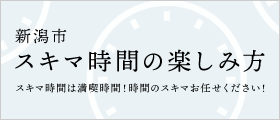令和7年3月21日 市長定例記者会見
最終更新日:2025年3月27日
市長定例記者会見
| 期日 | 令和7年3月21日(金曜) |
|---|---|
| 時間 | 午前10時00分から午前10時50分 |
| 場所 | 新潟市役所(本館3階 対策室) |
発表内容
質疑応答
- 避難指示の解除について
- 第41回新潟シティマラソン2025の開催について
- 市職員の軽装勤務の通年実施について
- 古町地域(旧三越跡地、西堀ローサ)について
- 下水道について
- 新潟交通のバスについて
- 公費解体について
- 新駅について
- 合併から20年経つことについて
配布資料
市長記者会見動画
令和7年3月21日開催記者会見の動画(クリックすると録画映像をご覧いただけます)(外部サイト)
![]()
発表内容
1.避難指示の解除
おはようございます。年度末になりまして、卒業式のシーズンとなりましたが、今日は記者会見ということでよろしくお願いいたします。
はじめに、能登半島地震発生後に発出していました「避難指示の解除」についてです。
地震発生後に余震や降雨によって土砂災害の発生などのおそれがあったことから西区の3地域、計19軒に対して避難指示を発出していました。
これまでに、地盤の安定が確認できた2地域7軒は、先行して1月に避難指示を解除しておりましたが、この度、残る1地域の西区大野においても、計器による計測やボーリング調査の結果から地盤の変状がないことが確認されましたので、本日付けで避難指示を解除いたします。
これにより、昨年1月3日に発出した避難指示は、すべて解除することになりますので発表いたします。
2.第41回新潟シティマラソン2025の開催
次に、「第41回新潟シティマラソン2025の開催」についてです。配布資料をご覧ください。
本市の一大スポーツイベントである「新潟シティマラソン」を10月12日の日曜日、三連休の中日(なかび)に開催します。
ご承知のように新潟シティマラソンは、柾谷小路や萬代橋といった街中や、信濃川、日本海など豊かな水辺をコースとし、デンカビッグスワンスタジアム発・陸上競技場着で行います。
今年も実施種目は、「マラソン」、「ファンラン」に加え、年齢や障がいの有無を問わず参加できる「ユニバーサルラン」の3種目を実施します。「マラソン」では「ふるさと納税枠」を新設し、一口4万2千円の寄付をいただいた市外在住者の方に出走権を進呈することといたしました。本大会をきっかけに、多くの方々が訪れていただき、本市の魅力に触れていただく機会となることを期待しています。
裏面をご覧ください。昨年からの佐渡トキマラソンとの連携企画も継続するとともに、本大会でしか手に入らない、魅力的な参加賞やオリジナル商品を用意しました。
申込受付を4月9日に開始します。市役所本庁舎前のカウントダウンボードなどを活用しながら、エントリー開始から大会当日に向け機運を醸成してまいります。多くの皆様のエントリーをお待ちしています。
3.市職員の軽装勤務の通年実施
次に、「市職員の軽装勤務の通年実施」についてです。
職員の勤務時の服装については、夏季の省エネ対策の一環として、毎年5月1日から10月31日までをクールビズ期間とし、ノー上着・ノーネクタイなどによる勤務を行ってきました。
また、近年は毎年の猛暑や働き方の多様化に伴い、官民問わず働く際の服装にも変化が現れてきています。
こうした中、今年度「働きやすい服装の推進」などをテーマに若手職員を中心とした庁内横断的な意見交換会を開催しました。そこでの意見を参考に、「業務能率の向上による市民サービスの向上」と「環境負荷低減への一層の機運醸成」を目的として、市民の皆様に不快感を与えることなく、気持ちよく市役所を利用いただけるよう基準を策定し、来月1日から、通年で軽装勤務を行うことといたしました。
なお、式典や外部の方との会議の場など、スーツやネクタイ着用が求められる場面においては、当然ながらその場面に適した対応を行うことになりますけれども、気候やTPOに応じて適切な服装を選択できるようにすることで、働きやすい職場づくりや業務能率の向上を図り、市民サービスの一層の向上と環境負荷低減への機運醸成につなげてまいりたいと考えております。
本日、市役所本館4階の広報課で軽装勤務を試行実施していますので、取材を希望される皆さまは、記者会見後、広報課職員へお声がけください。よろしくお願いします。
質疑応答
避難指示の解除について
(新潟日報)
避難指示の解除についてお伺いします。今、ご説明があったとおりで、重ねてになって恐縮なのですけれども、この地域についても、追加の工事等はせずとも安全であるという判断を市としてされたということでよろしいでしょうか。
(市長)
はい。そういうことになります。継続的な安全確認ですとか、地盤の調査をやってまいりましたけれども、特に変状が発生してこなかったと。一定の期間を通じてそうした調査をやってまいりましたけれども、そうしたことから、避難指示の解除を行いまして、一つの区切りを迎えたと認識しております。これからの地域の皆様の生活再建に引き続き全力で後押しをしていきたいと考えています。
(新潟日報)
まさに今おっしゃったように、1年以上の間、避難指示が出ていて、ご自宅に帰れない、あるいは再建しようにもいつ避難指示が解けるのかということで、対象地域12軒と少ないのですけれども、その前、1月に解除された方も含めて、すごく不安な1年をお過ごしだったと思います。改めて避難指示の対象地域に暮らす皆さんへの今後の支援というか、市のフォローというものは何かあるのでしょうか。
(市長)
まずはこの地域には住宅と商店があります。その中で継続して商業を続けたいという方もいらっしゃいますし、解体をやるという意向をお持ちの方もいらっしゃいます。いずれにいたしましても、先ほど申し上げたとおり、まずは地盤の安定が確認されたということを皆さんにしっかりとお伝えしながら、一方で、この地域内には土砂災害警戒区域ですとか、土砂災害特別警戒区域が含まれておりますので、解除後も引き続き工事に応じた緊急点検ですとか、安全確認などをやっていく必要があるのではないかと思っています。
(新潟日報)
住民の方も安心されると思いますので、引き続き市としてもフォローしていただけることをお願いしたいと思います。
(NHK)
避難指示の解除についてなのですけれども、可能であれば、この対象の地域12軒に何世帯の方が住んでいらっしゃったのかお伺いしたいのと、もし可能であれば、大野の一部の詳しくどのあたりかをお伺いできればありがたいです。
(市長)
住んでいた方は6世帯でいいですか。
(水野西区長)
今、私の手持ちがなくて、数字は押さえていますので、後ほどお答えさせていただきます。
(新潟日報)
避難指示の関連なのですけれども、まず大野における調査はいつからいつまで行ったのでしょうか。
(市長)
大野における調査は、昨年の10月3日から計測器を設置し、これまで約5か月間継続的に地盤の変状について計測を行ってまいりました。なお、ボーリング調査を2カ所実施いたしました。こうした対応によって、まとまった降雨や地形による顕著な変位量の増加はなく、変位量も基準値以下であり、地形に影響するような変状がなかったということです。
(新潟日報)
5か月間というと、今月の上旬くらいには終了したということになるのでしょうか。
(水野西区長)
そのとおりです。
(新潟日報)
今日は3月21日ということで、3月の上旬にある程度安全であるということを市は判断したうえで、先ほどほかの質問がありましたが、暮らす住民の方としては、一日も早く避難指示が解除されてほしいと願う気持ちもあった中で、3月上旬から今日まで避難指示がさらに続いたという、このタイムラグは何だったのでしょうか。
(水野西区長)
調査自体は上旬で終了しているのですけれども、その後の分析に数週間を要したということです。。
(新潟日報)
改めてですけれども、もし地盤の変状などが今後降雨によって起こり得る場合には、市の責任としての工事なども検討されていたということですけれども、そういった工事は今後一切行わないということで間違いないでしょうか。
(市長)
今後絶対行わないというようなことはないと思いますけれども、仮定の話ですので、まずは地形について安定しているということの結果を皆さんにお伝えしたいと思います。
(NST)
改めてなのですが、これで新潟市内で出されている避難指示はすべて解除ということでよろしかったでしょうか。
(市長)
はい。それでけっこうです。
(NST)
改めて市内の避難指示解除を受けて、市長としては次のフェーズに移ったという所感などはありますでしょうか。
(市長)
この避難指示を出した地域というのが、昨年の能登半島地震の発災によって非常に大きく被害を受けた地域の一つであると認識しております。1年以上かかったわけでありますけれども、今回の解除によって、長く自分の家や商売する場所が安全なのだろうかという不安をお持ちの方々も、今回発表することによってひと安心をしていただけるのではないかと考えておりますし、まさに先ほど申しました、新潟市は災害で課題の一つであった解除ができたことによって、一つの区切りを迎えたと認識しています。
第41回新潟シティマラソン2025の開催について
(新潟日報)
次に新潟マラソンなのですけれども、昨年から佐渡トキマラソンとの連携企画を始められて、今年で2回目だと思うのですけれども、昨年、実際佐渡と連携企画をやってみられて、その効果ですとか、そのあたりはいかがでしょうか。
(市長)
昨年から佐渡とトキマラソンの連携協定を行いまして、姉妹大会協定を締結しまして、今年で2回目の取組みということになりますけれども、ダブル完走メダルの取組みですとか、新潟、佐渡の特産品のブースを設置することで、参加者や来場者に魅力をアピールし、交流人口の拡大を図っていきたいと、こういう思いでやってきておりますけれども、前回大会でダブルエントリーが385人という参加になっております。
(新潟日報)
引き続きということで。
(市長)
新潟と佐渡の魅力を発信していければと思います。
(新潟日報)
また、今回からふるさと納税枠を作られるということですけれども、少し話は変わるかもしれませんが、新潟市はふるさと納税がなかなか苦戦している部分があろうかと思いますけれども、今回も含めて、市としてふるさと納税、いろいろなアイデアで取り組まれると思うのですけれども、今後もいろいろ考えていきたいと思っていらっしゃる部分というのはおありでしょうか。
(市長)
新潟市のふるさと納税につきましては、県内の他都市に比べますと比較的緩やかにやってきたのですけれども、時折ちょっと頑張ってほしいということで、担当の課にもお願いして、返礼品を増やしたりして取組みをやってきまして、今また米が不足しているということで、米などについては(納税額が)上がっているようです。
(新潟日報)
あまりこればかりというわけではないのですけれども、市民としては、出ていくよりは入ってきていただきたいというところがありますので。
(市長)
出ていく一方ですけれどもね。残念なんだけれども。
(新潟日報)
ぜひお願いいたします。
市職員の軽装勤務の通年実施について
(新潟日報)
ちなみに、軽装勤務については市長ご自身は、市長は対外的なお仕事もあって難しいのかなと。
(市長)
夏場はできるだけ軽装にしたいと思っているのですけれども、やはり外から来るお客様に会わない日が少ないものですから、どうしても上下スーツでネクタイをするようなこともありますけれども、そうでないときはできるだけ軽装で臨みたいと思っています。
(新潟日報)
若手職員を中心とした意見交換会の声を参考にされたということで、働きやすい職場づくりで、今おられる職員の方が働きやすくなると思うんですけれども、採用活動へのプラスの効果とか、影響といったものはどう見ていらっしゃるのかを伺えればと思います。
(市長)
やはり若手職員を中心にした意見交換の場におきましても、服装についても従来の決まり切った服装だけではなく、場面に応じた柔軟な対応を求める声があったという意見も頂きました。現在の働いている人たちの環境を見ますと、さまざまな服装で勤務している会社がだんだん増えておりますので、今回の取組みが若者の皆さんから新潟市役所が働く場として選んでもらえる理由の一つになればと思っています。
(日本経済新聞)
具体的に、これはだめだとか、ルールといったものをもう少し詳しく教えてください。
(市長)
詳しいことは担当のほうからですけれども、今回はあまりにもカジュアルな服装は不可とするなど、一定の基準を設けて、その基準内で軽装化に取り組むことにいたしました。
(梅田人事課長)
本日の配付資料にはお配りしておりませんが、例えば品位や信頼感を損なうような服装という観点で、サンダルですとか、髪の毛の色などについても一定の身だしなみの基準を設けてやってまいる予定です。
(日本経済新聞)
来庁者に関して周知するとか、そういった取組みなどはあるのでしょうか。
(市長)
特にありません。まずは新潟市役所の組織内でこうした新しい基準を作って、通年化でやっていこうということです。
古町地域(旧三越跡地、西堀ローサ)について
(新潟日報)
古町地域のことについて何点かお尋ねします。まず、三越についてなのですけれども、三越が閉店して明日で5年になりますが、三越が閉店したこと、そして閉店から5年、外から見る分にはあの部分が何も変わらないことについて、今、どうお感じでしょうか。
(市長)
三越の撤退から5年ということで、長く親しまれてきた古町の象徴のような存在がなくなったことについては、多くの市民の皆さんが寂しさを感じていると思いますし、また、それに伴って、古町地域も低迷をしていることに市民の皆さんも残念な思いをしているのではないかと考えています。1日も早く、旧三越跡地の再開発が促進されるように、我々も努力をしたいと思いますし、古町の活性化に向けてできることは取り組んでいきたいと考えています。
(新潟日報)
今度は西堀ローサについてなのですけれども、3月末でローサがなくなるわけではなくて、テナントがすべて撤退するわけですが、昭和51年に開業して、これまでローサが果たしてきた役割についてどう思われるか、そしてもし何かローサについて特に印象的な思い出などがあれば、お聞かせ願いたいのですが。
(市長)
昭和51年のオープンということですので、私が高校のときになるのでしょうか。それから約50年間、古町地区はもとより、新潟の賑わいや文化の発信地として大変多くの皆さんから愛され、また親しまれてきた商店街であると考えております。また、地下ということで、雨や雪にも影響されない場所ということで、営業終了というものは我々にとっても非常に寂しい思いがいたします。我々も寂しいですけれども、もちろんご商売をテナントに入ってやってこられた方々にとりましても、深い感慨があるのではないかと感じています。
(新潟日報)
そのローサを継続させるために、平成18年には9億円を市として貸し付けましたが、その後も地下開発の売り上げは大きく伸びることはなく、直近8年でいえば、8年連続赤字という結果でしたが、これは市としてどのような責任があるとお感じですか。
(市長)
さまざまな商売の形態といいますか、そういうことに影響されて、ローサも影響を受けて、やむなく(運営会社が)解散ということになります。その責任につきましては、同社の清算に向けた手続きの進捗を見つつ、適切なタイミングで判断をいたしたいと考えています。
(新潟日報)
今もお話がいろいろあったのですけれども、なくなるとはいえ、今もたくさんの人が愛していて、みんな大切だなと思っているとは思うのですが、市長としては、ローサが今も持っている価値、どのような価値があるとお考えになっていますか。
(市長)
まずは古町という、「にいがた2km(ニキロ)」の終・起点でもありますし、また、新潟といえば古町といわれるような過去に非常に、今から考えると想像を超えるような若い人や、さまざまな多くの方々がそこに買い物に行ったり、遊びに行ったりして賑わった地域であったわけであります。そうした価値というものは今も変わりませんけれども、時代の変化とともに、そうした役割も変化を見せているということで、今後も価値は決してそれほど大きく変わることはないと思うのですけれども、新たな利用の仕方について、今後、民間の皆さんとともに考えていきたいと考えています。
(UX)
三越跡地について、工事のほうが遅れるというような準備組合からの報告も市長は受けられたと思うのですけれども、その後、お話が進んでいる点があればお話しいただけると幸いです。
(市長)
その後進んでいるかどうか、担当のほうで、どうか分かりませんけれども、とりあえず、直接来ていただいて、今回、計画が少し頓挫したというところについては説明を受けたところであります。新聞報道などでは全国的にも中野サンプラザが900億程度の費用の増加によって中断をしたりと、非常に影響を受けていると思いますので、今回の状況については致し方ない部分があると思います。引き続きしっかり準備組合の皆さんと連携をとりながら、できるだけ早く開発事業が進むように取り組んでいきたいと考えております。
(佐藤都市計画課長)
今現在、準備組合のほうが施工業者を選定するにあたってのヒアリングを継続しているところでございまして、その結果が取りまったというところまではまだ聞いていないところでございます。
(UX)
先ほどもあった西堀ローサの件なのですが、先ほど思い出等も語っていただきましたが、今後市として対応していく点、構想等、少しでもあれば何か教えていただければと思います。
(市長)
場所柄からして、市民の皆さんから親しまれ、喜ばれる場所にしていく必要がまずあると思いますし、構想といいますか、これまでの経緯から考えると、同じようなやり方は通用しないと思いますので、多くの市民の皆さん、事業者の皆さんからご協力いただきながら調査などやって、実現可能なものから取り組んでいく必要があると思います。
下水道について
(新潟日報)
下水道についてなのですけれども、新潟市内で、例えば去年の8月にトラクターが転落するような大きな事故があったりと、道路陥没が相次いでいるわけですけれども、こういったことが市内で多く発生していることに関して、市長の受け止めをお願いします。
(市長)
老朽化によって、かなり老朽化して、こうした大きな事故につながっているということは大変重大なことと受け止めております。早期に緊急点検を行って、市民の皆さんから安心安全に道路などを活用してもらう必要があると考えております。また、下水道の機能につきましても、しっかり維持をしていくべきだと思います。
(新潟日報)
下水道機能の維持ということで、ウォーターPPPの導入ということで検討されていて、官民連携をより進めて、ヒト、モノ、カネでより安全な維持管理を進めていこうということなのですけれども、今後3,900キロと新潟市が管理している管路が非常に膨大ということで、どうしても人の目が行き届きにくいという面もあるかと思うのですけれども、今後の安全確認というか、安全対策の強化のために、どういったことが必要であるとお考えになるか、教えてください。
(市長)
しっかりと、老朽化対策を行いながら、日常から安全点検をやっていくということが課題になるのではないかと思います。
新潟交通のバスについて
(BSN)
新潟交通のバスについてお伺いします。春ダイヤで、本数は維持したのだけれども、運転手不足で運行距離が短縮されると発表されました。新潟市もバス運転手の免許取得に補助をしたりなど、運転手不足解消に支援を続けてきましたけれども、いまだ解消に至らないということで、この状況をどのように受け止めているかを教えてください。
(市長)
バス運転手の確保につきましては、全国的な運転手不足という中で、新潟の事業者におきましても精力的に運転手の確保に努めてきていると認識しております。引き続き、新潟市もさまざまな支援制度を作らせていただきましたので、それを十分活用していただきながら、必要な運転手を確保し、市民の皆様の足の確保、ネットワークの確保につなげていっていただきたいと考えています。
(BSN)
今後さらに支援を拡充するとか、そういう検討は今のところどうでしょうか。
(市長)
今までの支援で十分であるかどうかは正確にはまだ認識できておりませんけれども、まずは協定を結んで2年目ですので、まずは協定で結んだことを着実に実行、新潟交通さんと協力しながら、しっかり実行していきたいというふうに考えています。
(新潟日報)
連節バスについて何点か伺います。新年度の予算案に連節バスの更新に向けた計画を策定するということで、その費用が3,000万円盛り込まれているかと思います。市のほうで運転手不足の対策に寄与するため更新を目指していくというお考えかと思うのですが、今回の市議会のほうで、市ではなくて、新潟交通が購入すべきですとか、必要性から、そこから議論していかなければいけないということで、そういった声が挙がっていたかと思います。市長として、連節バスを更新する必要性について、どういうふうにお考えになっているか、まずお聞かせください。
(市長)
連節バスは1両で大量の人が、約2倍の旅客を運べるということで、大変貴重なバスであると考えております。運転手不足が指摘され、また大きな問題になる中で、市としても支援する中で、連節バスの購入というのは大切なことであると考えています。
(新潟日報)
市議会から上がっている声に対してはどのように応えていくか、これについてお聞かせください。
(市長)
もちろん、そういう声があっても決しておかしくはないと思いますけれども、ただし、今、交通事業者だけで運転手不足を解消しようとか、交通ネットワークを維持していくということが非常に困難になってきている現状にあると認識しております。そういう中で、事業者と官と新潟市民と協力してバス事業を支えていくといいますか、守っていく必要性が現在もあるのだろうと思います。
(新潟日報)
今後、更新計画を作っていく際なのですが、議会がいうように、更新を前提とするのではなくて、更新の必要性から議論していくというお考えはあるのでしょうか。
(市長)
議会がありますので、疑問があれば、議会の中でそれぞれご質問していただければと考えています。やり取りをさせていただければと思います。
(BSN)
全国的に運転手不足があるというお話がありましたけれども、そうした背景の中では運行距離の短縮というのはある程度は致し方ないことというようなお考えでしょうか。どうでしょうか。
(市長)
市民の皆さんにとっては非常に不便になって、不満足なことになると思いますけれども、事業者としては致し方ない部分があろうかと思っています。
公費解体について
(新潟日報)
能登半島地震の公費解体の関係なのですけれども、費用償還を再開する予定が今後あると思うのですけれども、今、スケジュールですとか、なぜこのタイミングで再開するかというねらいをお伺いできればと思います。
(市長)
今回の費用償還につきましては、そもそもが昨年3月31日までに契約をして、解体をするという方々を対象にしておりましたけれども、一つは3月31日を越えて自費解体をした方々は対象外になっていたということが一つ。もう1点は、公費解体を待てない、ハウスメーカーの皆さんが解体事業者を抱えていて待てない人たちが、公費解体の申込みを申請している人たちの中で、公費解体まで待つことができないという方々が費用償還に乗り換えるという方々を対象にして、今回、こういう救済策にさせていただいたということです。
(新潟日報)
今、市長がおっしゃられていた2点の方というか、そういった対象の人というのはけっこういらっしゃるのでしょうか。自費解体して対象外だった人ですとか、ハウスメーカーに乗り換えたりした人というのは。
(市長)
我々の見込みでは、一定数いるのではないかと考えています。今、申し込んでいるけれども、もう少し早く住宅を建て替えたいために自費で解体を早くしたいという方などを含めますと、かなりいらっしゃるのではないかと、一定程度いるのではないかと考えています。
(堀内循環社会推進課長)
今ほど市長がご説明したとおりなのですが、きっかけとなったことについて若干説明をさせていただきます。公費解体、費用償還を含む申請への締め切りが昨年12月27日で終わっております。その後、1月9日から環境省も入って、公費解体事業連絡調整会議というものを2週間に1回開催しているわけでございますが、その中で、解体業者のほうから解体に入ると動産とか公共インフラの切断が終わっていなくて、解体にかかれない人が出始めているという指摘がありましたので、2月6日から電話がけのアンケート200件近く担当課のほうでやらせていただきますと、公費解体を急ぐ、一刻も早く公費解体をやってくれというご意見が20件程度ほどございました。それと同時に、今ほど市長から説明があった費用償還、これは3月31日までに業者と契約をして、自費で解体したあと、公のほうに費用を請求するといった方々についても、3月31日までというのは非常にタイトだったのではないかというお声がアンケートをかけている中でも並行的にその声が聞こえてきましたので、環境省のほうと協議をいたしまして、協議が整ったので費用償還の再開をするということでございます。予定としては、4月7日から6月末にかけて申請の受付を廃棄物対策課のほうでやる予定でございます。本日夕刻、市のホームページで公表いたしまして、4月6日の市報にいがたに掲載予定でございます。
(新潟日報)
先ほど市長が、一定数おられるとおっしゃったのですけれども、ある程度どのくらいの人が申し込みそうだというのは、だいたい見込みは何十件とか何百件とか見込みはあるのでしょうか。
(堀内循環社会推進課長)
50件程度は出てくるのだろうと思っております。今、公費解体は2月末で430件、費用償還も含めてきておりますので、残りの部分が500ちょっとあるのですが、そのうちの1割くらい、新規の費用償還も含めてでございますが、出てくるのではないかと読んでいるところでございます。
(新潟日報)
最後に市長に伺いたいのですけれども、公費解体4月からスピードアップして数を増やしていかれると思うのですけれども、そこら辺の見通しも含めて、昨年の7月だったか8月に、市長も公費解体は市の責任でやっていくというお話をされていたので、見通しも含めて、今後の取組みについて、一言を頂けたらと思います。
(市長)
少しお待たせした方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、チーム数を段階的に増やしてまいりまして、現在は95チーム、37チーム体制から元請、下請の皆さんが増えまして、95チーム体制に増加させる予定です。2月は積雪期でしたけれども、解体が61件ということで、過去最高になりました。4月からは目標としては100件くらいを目標に解体を進めていきたいと考えております。以前から申し上げているとおり、10月までにはしっかり解体が進むように努力をしてまいりたいと考えています。
新駅について
(TeNY)
上所駅ができたということで、このタイミングで聞いてみたいのですけれども、新潟市内のほかにも仮称ですが、江南駅新設についても議論になっているようですが、それの進捗状況について、市長が把握していることであったり、また実現性についての考えなどがあればお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。
(市長)
江南駅につきましては、昨年度の線引きの見直しの中で候補地の一つに指定されたと認識しております。江南駅の実現に向けては組合、準備組合でしょうか、準備組合の皆さんがまちづくりに取り組んでいく一環の中で駅ができるものと考えております。ぜひ、今、開発行為のほうが熟度が遅いというようなことで調整しているようですので、引き続き、新潟市からも協力しながら推進が図られるように努めてまいりたいと考えております。
合併から20年経つことについて
(新潟日報)
新潟市が合併して3月でちょうど20年になるかと思います。巻町がたしか10月だったと思うので、今の形ではないのですけれども、いわゆる大きな新潟市ができて20年になるわけですけれども、市長はこの20年を見て、新潟市はどのように変わったか、あるいは合併当時に思い描いた新潟市の姿というのはどれくらい実現できたとお考えですか。
(市長)
合併して20年ということですけれども、新潟市という意味では非常に大きく発展をしてきていると認識しております。ただし、郊外部の方々からは、合併の効果が十分恩恵を受けていないという不満の声があるということも承知しております。この合併を実現できた理由として、やはり日本海側に仙台と同じように100万都市を目指そうという意欲的な方々がその推進力になって、たくさんの市、町が合併に参画をして実現できたということから考えると、その後は人口減少に直面して人口も頭打ちになり、むしろ徐々に減ってきているというようなことについては、さらに人口減少対策を新潟市の最重要課題として全力で我々は取り組んでいく必要があると認識しています。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()

 閉じる
閉じる